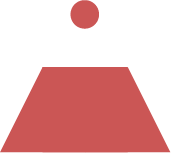女人禁制の寺院が多かった時代に女性の参拝を特別に認めていた室生寺は、「女人高野」として広く親しまれてきました。
その室生寺の周辺にある観光スポットを四景図として表現し、それぞれの場所を象徴するシンボルを組み込んでいます。
また、室生寺は桜の名所としても知られているため、全体のコンセプトカラーは落ち着いたピンク色を採用しています。
女人高野 四景図
高野山は、近代まで「女人結界」が定められ、女性たちの参拝は叶いませんでした。そんな時代でも、身内の冥福と、明日の安寧を願う女性たちの声に耳を傾ける「女人高野」と呼ばれるお寺があったのです。
優美な曲線を描くお堂の屋根、静かに願いを聴く柔和なお顔の仏像、四季の移ろいを移す樹々。これらが調和した空間を「名所図会(めいしょずえ)」は見事に実写し、表現しました。
また、そこに描かれた「女人高野」は時を超え、女性と共に今に息づき、誇れる女性たちを癒し続けています。
〈佛隆寺〉
創建は、弘法大使の弟子・賢恵(けんね)、または興福寺の修円(しゅえん)と言われています。本堂には、本尊の十一面観音菩薩立像、弘法大使像、堅恵坐像などが、辻堂には鎌倉時代末期の地蔵石仏が祀られています。境内には、重要文化財で賢恵廟とも呼ばれる石室と、弘法大使が唐から持ち帰ったとされる茶臼が寺宝として残っています。
奈良県指定天然記念物である桜の巨樹は、奈良県下では最大かつ最古といわれ、威厳と優美さ漂う姿が、多くの人々を魅了しています。
〈大野寺〉
役行者(えんのおづぬ)が開き、弘法大使が室生寺開創とともに建立したと伝わっています。対岸の切り取った岸壁には弥勒仏が線刻されており、高さ13.8mと国内で最も高い磨崖仏です。
本堂にある重要文化財・地蔵菩薩立像は、後頭部から背面全体が炭化していますが、これには無実の娘を火あぶりの刑から救ったという伝説があり、「身代わり地蔵」の呼び名でも親しまれています。春には境内の枝垂れ桜が見事に咲き誇り、県内屈指の景観地としても知られています。
〈女人高野 室生寺〉
真言宗の重要な道標のひとつとして、室生山の山麓から中腹に広がる山岳寺院が室生寺です。同じ真言宗で女人禁制だった高野山金剛峯寺に対し、女人の参拝を受け入れ、信仰を集めました。室町時代以前の建造物は国指定文化財で、本堂、金堂、五重塔は国宝に指定されいてます。
五重塔は日本最小の高さ16mの古塔で、女人高野にふさわしい珠玉の美しさをまとっています。
〈安産寺〉
重要文化財に指定されている地蔵菩薩立像は、子安地蔵とも呼ばれ、安産・子授けの信仰を集め、多くの女性が参拝に訪れます。
その昔、豪雨で宇陀川が増水した際、上流から流れつき、その美しく優しい姿に見とれた村人たちが、お堂を構えて安置したのが、安産寺と伝えられています。
一説には、室生寺金堂の本尊と酷似しているため、近世に室生寺から移されたとも考えられています。