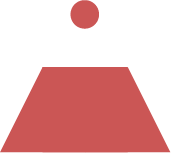2020年8月19日
橋本沙也加
(1)テキストの第一部(第一章から第四章まで)を読み、各章の概要をそれぞれ400字ずつでまとめる(1,600字程度)。
(1−1)第1章「作られる場所1ー地球史・生命史の観点から(原田憲一)」要約
芸術環境は、地球史と密接な関係を持つ。生命論的自然観の方が有効であり、「地球と生き物の共進化ー自然環境と生き物の多様化に景観の美化」を示し、生命誌的意義が必要不可欠である。
地球を含む太陽系は、経年の相互作用により形成された地球資源の過去と現在の重なりが、調和のとれた多様な美しさを生んでいる。その中でも、人間固有の行動である造形能力を活かして「生きる場をより美しくしよう」という人間の進化は、芸術的営為の神秘である。人間は、意図的に生活空間全体を美化する、
すなわち「芸術環境」を創造する生命史上初の生き物である。「西欧近代を起源とする生き方」を行き過ぎた形で生活に取り入れた私たちは、生命史の本質に立ち返り学ぶべきである。私たちの生活そのものが「この美しい地球社会を繋ぐこと」をビジョンとし、芸術環境を創造していくことが大切である。(367文字)
(1ー2)「第2章 作られる場所2ー芸術・環境・地域学(中路正恒)」要約
「作られる場」は、経験、環境、地域が密接に関わる。芸術の奢侈との関係性では、欲望への人々の衝動を律するべきである。ルソーの言葉にあるように「人間には、すべての人がその時間と配慮をささげるべきより高貴な目的がある」、その本質を探求することこそ、内なる欲望から本来の芸術や学問に触れることができるのではないか。「経験の中にある起源と作用」こそが芸術の意義を持ち、日常的な経験を切り離しては存在しない。生命のたどる時間は、環境に調和し適応する過程により、自らを豊かにしているプロセスであり、その美しさ<歓喜の知覚>こそが芸術の根源である。また、どれだけ深く広く人々の生の根拠を表現しつづけることができるかが重要である。日常にこそ芸術は宿り、その適応を求めることこそ、創造活動である。それによる新たな世界を見たときの「心を浮き立たせるもの」が芸術に一層の光を与えうる。(381文字)
(1ー3)「第3章 芸術環境としての造形(岩城見一)」要約
「芸術環境」は、「芸術という環境」と「芸術の環境」という大きく分けて二つの関係あり、その相互関係を見つめながら、「芸術という環境」の「造形」に絞って論じている。芸術のグローバル化は、西洋制度の波及とともに明治期の日本にも影響を及ぼし、東アジアにも伝播した。これにより土着の伝統文化とグローバルな西洋文化との葛藤の歴史が生まれた。また、資本主義経済の抽象的な美術市場で成長し、現代美術の異常な高騰を生み出し破錠した。表面化した価値が内面(モチーフの解釈やメッセージ性など)を失ったことに、「地域的」な意義を考え直す必要がある。芸術環境は、時代の流れとともに、今も変化している事実こそが本質である。造形は、モチーフを形あるものに表現する営みを指す。表現は、人々に世界の見方を与える知的活動とされ、生命力を与えてくれる。 芸術環境は常に変化し続けることを受け止め、造形から発せられるエネルギーに心を傾けることを示唆している。(409文字)
(1ー4)「第4章 芸術環境としての風景─歴史的重層性と断絶(安西信一)」要約
芸術環境としての「風景」とは、自然を人工的な枠組みの中で安全性が確保された美的空間で鑑賞する装置であり、自然とアートの中間が特徴である。風景に含まれる崇高の概念は、特に芸術環境を超えて、破壊的・暴力的な要素が内在する。世界が審美化されている傾向として捉えられた弊害として、芸術の境が複雑化し、本質の視野が薄れていることを表した。中でも、美的でない有用性・機能性・効率性、さらに経済性、倫理性、社会性、政治性の側面が含まれるものを美化すること、本来の芸術性の高いものと同列扱いすること自体が疑問である。メッセージ性の高低差は、時代に残り続け、倫理・経済・政治等々との解決の困難な衝突、矛盾、重層が生じる。これを少しでも回避するには、当該の場所の歴史的重層性と断絶に注意深く耳を傾けることが重要である。重歴史的重層性への断続と美化の存在に対して対峙し、芸術本質への傾聴をし続けることにこそ意味がある。(399文字)
(2)事例の考察
ここでは、本書(注1)で記された「芸術環境」をとりあげ、その本質的価値と起源について考察を深めたい。芸術環境とは、人間の芸術的営みであり、自らの生きる場をより良くしようとする行為として、自己と自然や社会との構築的関係を示すための造語とされる。この芸術環境は、人間固有の本質的な造形能力であり、人類の営みそのものに価値を見出すものと言える。しかしながら、時にそれは、本質を見失い奢侈の奴隷として生み出されることも多く、これは芸術そのものの性とも言える。しかし、人々が奢侈を求めて時間や労力、自らの価値観までもを売り払っている間、淡々と本質の価値を求めて努力し、葛藤し続けることで、そこには「自らの芸術性」が宿ると本書(注1)では論じられている。
この「自らの芸術性」の価値を形成する要素の一つとして筆者は、固有性、希少性、意味性、共感性が特に関係するのではないかと考える。「自らの」という言葉には「固有の」の表現が許された環境を意味しており、そこに向かう人間が持つ意思や経験によって芸術の意味性が生まれると言って良いのではないだろうか。自らの芸術性が時流の共感をどこまで得られるかによって、認知度の高さにも影響し、「賞賛される芸術と埋もれる芸術」に分けられるのではないだろうか。だが、この共感性が高まれば高まるほど、奢侈に近づくと言っても過言ではない。奢侈と関係する本質的理由は、本書(注1)の芸術環境の指摘でもあった「人類の営みの根幹に芸術が位置付けられること」にあると筆者は考えている。私たちは、生きるために「営み」をせずにはいられず、その豊かさの基準は経済的、物的、精神的豊かさの価値に相関することも事実であるためであろう。もちろん、人によって豊かさを求める価値の比重は異なる。このように芸術というものの価値は、たとえ本質的価値(自らの芸術性)が備わっていようとも、人々の共感性が高まれば高まるほど、奢侈に近づいてしまう性質を持つのだ。皮肉なもので、それが芸術が成し得る「唯一無二の価値」であるとも言える。よって、芸術環境とは、それを芸術と「自ら」が発見し、表現し、批評した時点で生み出されていると言うことではないだろうか。
そして、芸術環境は、社会学的視点からも理解することができる。社会学者の岸(2015)は、人々の営み(生活・日常)を丹念に見聞し、社会学的視点から人々の生活史を考察してきた。岸(2015)は、人々の何気ない営みの繰り返しの中には、なんとも言えない「美しさ」が宿っており、これに遜色をできるだけ加えずに記録することを意識していると記す(注2)。そして、そのものに、遜色を加えることは、一種の暴力的行為だと理解した上で、それでも探求している。それはおそらく岸(2015)なりの芸術的活動と言っても良いだろうが、彼自身は、奢侈的芸術性はないと断った上で、「活動そのものから得られるものの美しさ」を強調している。その中で「かけがえのないもの」へのロマン、すなわち希少性の価値について論じている(注2)。人々の生活物語に関係する対象物そのものについて「①失われてしまった後に見出された場合」、「②失われてしまった後に見出されなかった場合」、「③そもそも最初から存在もせず、それゆえ失われることさえない場合」、「④そこに最初から存在し、そして失われることもなく、だが誰の目にも触れられなかった場合」の対象物の希少性について指摘しているのだ。これらは、①から④に連れて、希少性が高くなっていると岸(2015)は、指摘しており、それぞれの「場合」という背景を、人々が発見した時に、その対象物への「かけがえのない美しさ」が生み出されると指摘した。筆者は、この「かけがえのない美しさ」の発見と表現に、ある一定数の人々が共感した時、「営みという背景」と合わせて芸術的価値が備わるのではないかと推察する。すなわち芸術環境の原点的を示しているのではないだろうか、芸術環境の第一歩はこういった人間の営みになんらかの意味付けを行うところから、始まることがよく理解できる。その「自ら」の解釈による意味性を持たせるところに芸術の起源があるのではないだろうか。
芸術そのものは、人を通して解釈を付加していることには他ならず、これも一種の暴力的行為になりかねないことも、芸術環境を学習において自問自答し、私自身の解釈というものを表現する必要があるだろう。
引用:
(注1)松井利夫・上村博編『芸術環境を育てるために』(京都造形芸術大学・東北芸術工科大学出版局藝術学舎、2020年)
(注2)岸政彦『断片的なものの社会学』(朝日出版社、2015年)